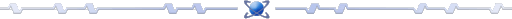 |
シギショアラ
この街の歴史は古くローマ軍が駐屯していた記録が残っているそうです。1191年にドイツ人が入植したことに始まっていると
言います。15~16世紀にギルドを持つ城壁都市として栄え、街を守るため其々のギルドで見張り塔を建てました。現在でも
「靴職人塔」「肉屋塔」ほか9つの見張り塔が残っています。14世紀に街が商工ギルドによる自治都市となったことを記念して
時計塔が建てられました。高さ64メートル。現在では歴史博物館になっています。展望テラスからはシギショアラの旧市街が
一望でき、東京はこちら方向に8890Kmと矢印が鉄板の上に書かれていました。
今回の旅行では、一度も日本人の旅行者に会っておらず、何処にでも旅行している日本人には出合いませんでしたが
このホテルで、二人組の男性の東洋人に出会いました。初め中国人かな?と思っていると、日本語を話しているので、「日本人
ですか?」と尋ねると、東京から来た若い勤め人だと言う事です。日本からの旅行者はまだまだこの地方に来る人は少ない
ようです。乗り継いだフランクフルトまで帰ってくると、日本人旅行者が大勢いましたが・・・。
ここでも、一人旅の女性と二人で、朝の散策に出ました。木造りの屋根のある階段を登って、丘の上の教会へ
そして街の中を少しだけ散策。朝の街中は静かで風情がありました。
帰りがけに、小さなお土産物屋に入りましたら、可愛いテーブルの上に置くキャンドル・スタンドがありました。
日本でも見かけた事のある輸入品です。気に行ったので一つ買い求めました。多分ここで買った方が安いだろうなんて
考えたからです。
泊まったホテル=シギショアラ ホテル内の会議室の壁には500年前のフレスコ画が残っていました。
|
 |
 |
 |
 |
| ホテル・シギショアラ |
時計塔から見た街並み |
500年前の壁画 |
珍しい形の教会 |
| |
|
|
|
|
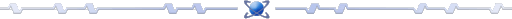 |
ビエルタン要塞教会
 |
この教会は創設当時はカトリック教会でしたが、1541年にルター派(プロテスタント)に移行しました。
この地域に要塞教会は幾つかありますが、三重の壁に囲まれているのは此処だけだそうです。
籠城に備え、数々の設備が作られています。教会の中の椅子は、壁沿いに男性が座り、女性や子供は
敵から守るため、真ん中に座る様に設計されています。祭壇の横の聖具室には、16の鍵を付けてあり
宝物が盗まれまれないように作られています。1900年のパリ万博では、この技術に対して一等賞を
送っています。教会の入口の鍵のかけ方の実演をして見せてくれました。一つのカギ穴で何度も鍵の上や
下側を使って開け閉めをしています。この光景も「世界ふしぎ発見」で見た記憶があります。
教会の外には「お仕置き部屋」が再現されていました。カトリック教会だった時代、離婚が認められず
仲たがいした夫婦は此処に入れられ、反省を促されたと言いますが、「こんな狭い部屋で一緒にいると
かえって、益々鼻につくのではないか?}と笑ったりしたものでした。
|
|
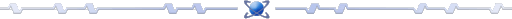 |
ブラショフ
ブラショフで有名な「黒の教会」では、夕方から始まるパイプオルガンのコンサートを鑑賞しました。
教会で聞くコンサートは風情があります。パイプオルガンが設置されているコンサート・ホールでの演奏は
聞いた事がありますが、こういった機会には今まで出会いませんでしたから好い思い出となりました。
黒の教会は、ハプスブルグ家の砲撃で外壁が黒く焼けた事から「黒の教会」と呼ばれる様になったと
言う事です。高さ65m。トランシルヴァニア地方最大の後期ゴシック教会。4000本のパイプと4つの
鍵盤を備えた、ルーマニアで2番目に大きなパイプオルガンを備えています。
ヨーロッパの街にはたいていある中央の広場(スファトゥルイ広場)で運転手のドリンさんと記念撮影(写真上)
後ろのトゥンパ山には「BRASOV」の名前を書いた看板がある。(写真下)は黒の教会の時計塔の絵柄。
泊まったホテルはアロー・パレス→窓からの風景、部屋の様子も素敵なホテル。
ここではもう一人の一人旅の方と朝食後、近くを散策に出ました。ホテルの正面入り口から道路を挟んで
向こうの通りに露天商が店を出していたので、二人で見るだけショッピングに行きましたら、おばちゃんに
声を掛けられ、片言で話してる中、「二つ買ったらまけるか?」と言ったら」「まける」と言うので、刺繍の
テーブルクロスを買う事になりました。買う予定ではなかったのですが・・・・・。でも今になると買っていて
良かった。我が家の丸いテーブルに良く似合います。一枚600円なり。露店は安い。
またこの街では、スーパーマケットとデパートに行きました。スーパーマケットでは、沢山のハーブティーと
テーブル用ナプキンを購入。デパートでも、テーブル用ナプキンを購入。スーパーのとは格段に値段が
高い。でもやはり高級でした。戻って来て使って見るとよく判ります。
|

 |
 |
(左)プレジメル要塞教会は教会を囲む城塞部分に部屋が作られている
のが特徴です。ここには食糧庫を含め約270の部屋が作られ、敵に攻め
られた時、立て籠もって戦えるようになっています。13世紀この地方で最も
強固な城塞でした。ガイドの話を聞いていると、この辺りは当時、教会に
避難場所を作っていたと思われ、城塞教会を多く作っています。この教会は
当初カトリック教会でしたが後にプロテスタント教会に変わりました。中庭の
中央に教会の礼拝堂が建てられています。
(右)はブラショフ聖ニコラエ教会の墓地の入口。フレスコ画が綺麗に
描かれています。ブラショフ聖ニコラエ教会の内部は今まで見てきた
正教教会のどれよりも美しく驚きでした。ルーマニアの墓地は色々で
面白いですが、今でも土葬されているようです。お花などが植えてあり
綺麗ではありますが、ルーマニア人は、亡くなった人のお墓には、あまり
お参りに来ないそうです。 |
|
 |
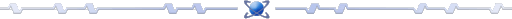 |
ブラン城
ドラキュラの居城のモデルとなったお城。もっと古めかしく、不気味な城を想像していたの
ですが、綺麗に整備された素敵なお城でした。観光客も多く、人気の観光地なのだろうと思わ
れる場所です。一人で座ってグループの買い物が終わるのを待っていると、子供連れの
外国人の男性に声をかけられましたが、英語力が高くないので、よくは判りかねました。
「ここは二つの地域の間にあり、その間の道は美しい所で、近くの町までタクシーでも
行けるる。」と言ってるように、聞こえました。「ここは気に入ったか?」と言うので「好きだ。」と
答えました。色々説明してくれたのですが、よく理解できず、言葉が解ると旅が楽しいものに
なるだろうと、残念でした。
「Bye-Bye! Good luck! Have a nice day」と言うと「You too」と言ってくれ別れました。
ここではルーマニアの民族衣装の刺繍のブラウスを購入しました。手作りの刺繍が施されて
いて、肌触りの良い綿製品です。
|
 |
|
|
 |
シナイア僧院
「カルパチアの真珠」と謳われているシナイア・リゾートはカルパチア山脈の麓、標高800mの位置にあり
18世紀にはブカレストの王侯貴族達の別荘地でもありました。現在ではブカレストから車で2~3時間で
来られることから夏の避暑地、冬のスキーリゾートとして大変人気の地だと言います。
その地にあるシナイア僧院は1846年にカロル一世が建てた古い教会です。 |
|
|
|
|
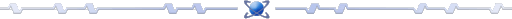 |
ペレシュ城
1875年からカロル一世がルーマニア王室の夏の離宮として数十年の歳月をかけて建てた、ル-マニアで最も華麗なお城と言われて
いる建物です。入館時には靴の上にカバーを付けなくてはなりませんし、撮影にはフォトチャージがかかります。代金を支払った人は胸に
証明証をぶら下げていなくてはいけません。各部屋にはカロル一世が収集した美術品や陶器、武器、書籍、宝飾品が陳列されています。
また ヨーロッパでは最初にセントラル・ヒーティングや電気が備えられたモダンなドイツ・ヌネッサンス様式のお城でもありす。
敷地面積3500㎡ 400人以上の工芸家や何千人もの労働者によって完成しました。クルミの木には、見事なまでの彫刻がなされ
見る者を圧倒しています。天井のステンドグラスや窓やドアにもステンドグラスが使われている所があり、モダンな雰囲気を出しています。
フランス系の城やドイツで見たお城などは、金が多く使われて気疲れしてしまいますが、木の彫刻の豪華さは安心感が感じられます。
しかし庶民として育った私などは、もっとシンプルで質素な家が理想です。見物人となるのがベストな建物でした。この中には小劇場も
作られていました。壁を描いたのは、かの有名な画家グスタフ・クリムトでした。すぐにクリムトと判る絵です。パリのオペラ座の天井画を
描いたシャガールを思い出しました。絵を描く事を趣味とする私としても「好いもの見る機会があったわ!」という気分でした。
|
|
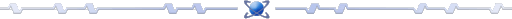
CARU CU BERE
この意味はルーマニア語で、「ビールを乗せた馬車」と言うそうです。
ブカレスト市で人気NO.1のビア・ホールだそうです。旅の最後は
ビア・ホールと言う事になりました。民族舞踊ショーやスッタフ全員
の行進があり、挨拶に出てきます。貴族の館だった所を改装して
レストランにしたと聞きました。大きなホールには人が一杯で
大声を出さないと聞こえません。喧噪のディナー件飲み会と言う
最後の晩餐となりました。 余談ですが、今回のグローバルの
添乗員さんは、とても好い方でした。この旅行社のツアー・コンダク
ターさんは良いと、評判ではありますが、目立ないが細やかな
心遣いで、素敵な女性でした。大柄な容姿とのギャップに驚き
でした。添乗員さんのお陰で楽しい旅、思い出に残る旅となる
事を感じたものでした。特に一人旅だとそれを強く感じます。
お世話になりました。ありがとう ございました。
|
 |
 |
|